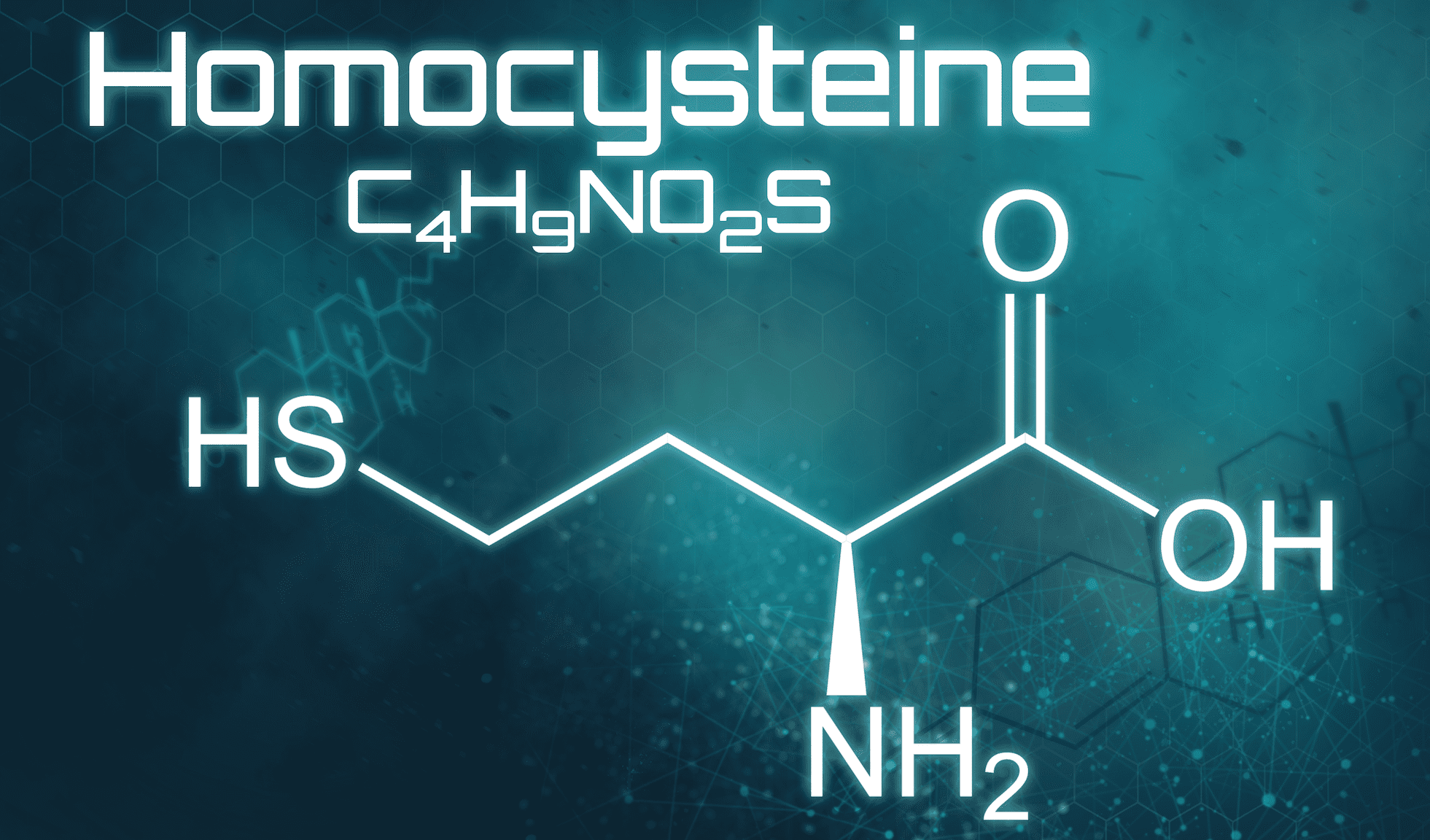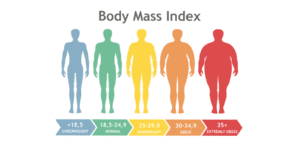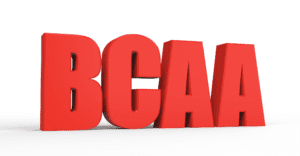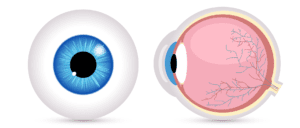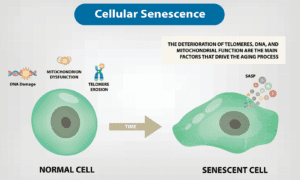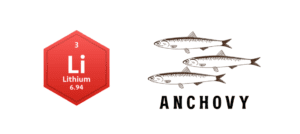1960年代、ハーバード大学の病理学者キルマー・マッカリー博士は、血液中のアミノ酸「ホモシステイン」が動脈硬化の原因になることを発見しました。博士は、ビタミンB群の不足が血管を硬化させると指摘しましたが、当時の医学界には受け入れられず、長く無視されてきました。
しかし後の大規模研究によって博士の説は正しかったことが証明され、ホモシステインが心筋梗塞や脳卒中、認知症など、多くの疾患のリスク因子であることが明らかになりました。
ホモシステインは、肉や乳製品に多く含まれるアミノ酸メチオニンの代謝過程で一時的に生成されます。血中濃度が高くなると血管内皮を傷つけ、動脈硬化を進める要因となります。アメリカやカナダでは1998年に葉酸の食品添加が始まり、国民の平均値は8〜9 µmol/Lに低下し、脳卒中による死亡率も減少しました。
一方で、日本人にはホモシステインが高くなりやすい体質の人が少なくありません。葉酸を活性型(5-MTHF)に変える酵素「MTHFR」の働きが弱い遺伝子型をもつ人が多く、全体の約30〜40%、そのうち約15〜20%は特にホモシステインが高値になりやすいタイプです。このような人は通常の葉酸では十分に代謝できず、ビタミンB6・B12・葉酸が不足すると血中ホモシステインが上昇します。
ホモシステインを正常に保つためには、ビタミンB6、B12、活性型葉酸(5-MTHF)の摂取が欠かせません。また、N-アセチルシステイン(NAC)という抗酸化物質を1,800mg/日程度摂取すると、ホモシステインの排出を促す働きも報告されています。NACはサプリメントとして利用されることもあります。さらに、地中海食のように野菜や魚、オリーブオイルを中心とした食事は、ホモシステイン値を下げるだけでなく、炎症を抑え、寿命を延ばすことにもつながります。
マッカリー博士は2025年、91歳で亡くなりましたが、その研究は今も私たちの健康を支えています。健康診断や医療機関でホモシステイン値を調べてみましょう。それが、心臓と脳を守る第一歩となります。